目次
哀糸豪竹の読み方と意味
■ 四字熟語
哀糸豪竹(あいしごうちく)
■ 読み方
あいしごうちく
■ 意味
「哀糸豪竹」とは、琴や糸の楽器が奏でる哀しみの音と、竹の管楽器が奏でる力強い音を指す言葉です。転じて、音楽の繊細さと力強さの調和、または感情表現の幅広さを意味します。
- 「哀糸」…琴や三味線など糸でできた弦楽器が発する哀切な音色。
- 「豪竹」…笛や尺八など竹でできた管楽器が発する勇壮な音色。
感情を込めた豊かな音楽表現や、芸術性の深さを象徴する表現です。
哀糸豪竹の語源と出典
■ 出典
中国古典音楽や文献に見られる造語的表現。特定の典拠はありませんが、文人の詩文や音楽評論において用いられることがある言葉です。
糸=弦、竹=笛という、中国楽器の基本分類に基づいています。
哀糸豪竹の使い方と例文
■ 用例・使い方
- 演奏会では哀糸豪竹が見事に調和し、聴衆を魅了した。
- 哀糸豪竹の響きに心が震える。
- その作曲家の作品は哀糸豪竹を極めたような構成だった。
哀糸豪竹と関連する四字熟語
以下は、「哀糸豪竹」と近い意味・芸術的な感性や表現を含む四字熟語です。
| 四字熟語 | 読み方 | 意味 |
|---|---|---|
| 詩歌管弦 | しいかかんげん | 詩や音楽など風雅な芸術活動のこと |
| 高山流水 | こうざんりゅうすい | 高尚な音楽、または知音(心を通わせる人)の存在を指す |
| 琴瑟相和 | きんしつそうわ | 夫婦や仲間が心を通わせて調和していること |
| 音吐朗々 | おんとろうろう | 音の発し方がはっきりしていて美しいこと |
| 能文能武 | のうぶんのうぶ | 文芸にも武にも優れていること |
哀糸豪竹が使われるシーンとは?
■ 音楽や芸術の評論
演奏の情感・技術を豊かに表現したいときに使える語句です。
■ 詩的・文学的な表現
文章や詩の中で、音の美しさや感情の広がりを象徴的に表す際に使われます。
■ 感性の豊かさを語る場面
人や作品における「繊細さと力強さの両立」を表したいときに適した言葉です。
まとめ:哀糸豪竹は、音楽と感情の調和を象徴する言葉
「哀糸豪竹」は、繊細な哀しみの音と、豪快で力強い音の対比と融合を表す美しい四字熟語です。
音楽だけでなく、芸術や人の表現にも応用できる、奥深い情緒を持つ表現として、文学や詩にもふさわしい語です。
.png)
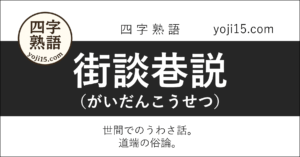
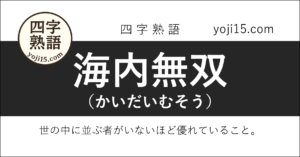
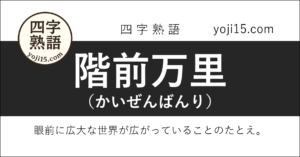
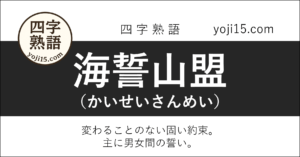
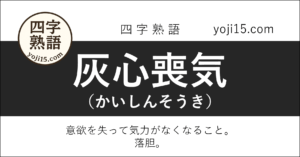
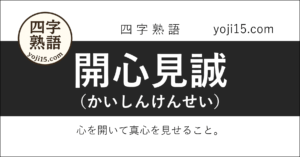
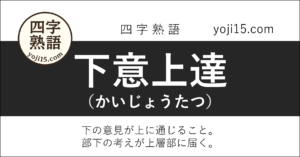
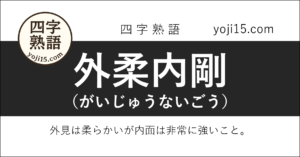
コメント