目次
一韻到底の読み方と意味
読み方
いちいんとうてい
意味
「一韻到底」とは、詩や文章において、最初に決めた同じ韻(音の響き)を最後まで通すことを意味します。
韻律の統一感を保ち、全体の調和と美しさを生み出すための表現技法の一つです。
転じて、一貫性を保ち続けることのたとえとしても使われます。
一韻到底の語源・由来
出典
中国の古典詩文に見られる韻文作法から生まれた言葉です。
古代漢詩や律詩では、句末の発音を揃える「押韻」が重要視され、最初に決めた韻脚(韻の種類)を最後まで変えないことを「一韻到底」と呼びました。
一韻到底の使い方と例文
使用シーンのポイント
- 漢詩や和歌の作法を説明するとき
- 文章や演説で一貫性を保つ姿勢を強調するとき
- 芸術的統一感を評価するとき
例文
- 彼の漢詩は、一韻到底の技巧が見事であった。
- 言葉選びにぶれがなく、一韻到底のごとき演説だった。
- 一韻到底を守ることで、詩全体に重厚な響きが生まれる。
一韻到底と関連する四字熟語
| 四字熟語 | 読み方 | 意味 |
|---|---|---|
| 一気呵成 | いっきかせい | 一気に物事を仕上げること |
| 一貫不易 | いっかんふえき | 最初から最後まで変わらないこと |
| 首尾一貫 | しゅびいっかん | 最初から最後まで筋が通っていること |
| 文質彬彬 | ぶんしつひんぴん | 内容と形式が調和して美しいこと |
| 統一調和 | とういつちょうわ | 全体がよくまとまり調和していること |
まとめ:一韻到底は芸術的統一感を象徴する言葉
「一韻到底」は、詩文において韻律を一貫させる技巧であり、転じて物事の統一感や一貫性を保つ姿勢を表す四字熟語です。
文学や芸術分野だけでなく、日常会話でも比喩的に使えるため、覚えておくと表現の幅が広がります。
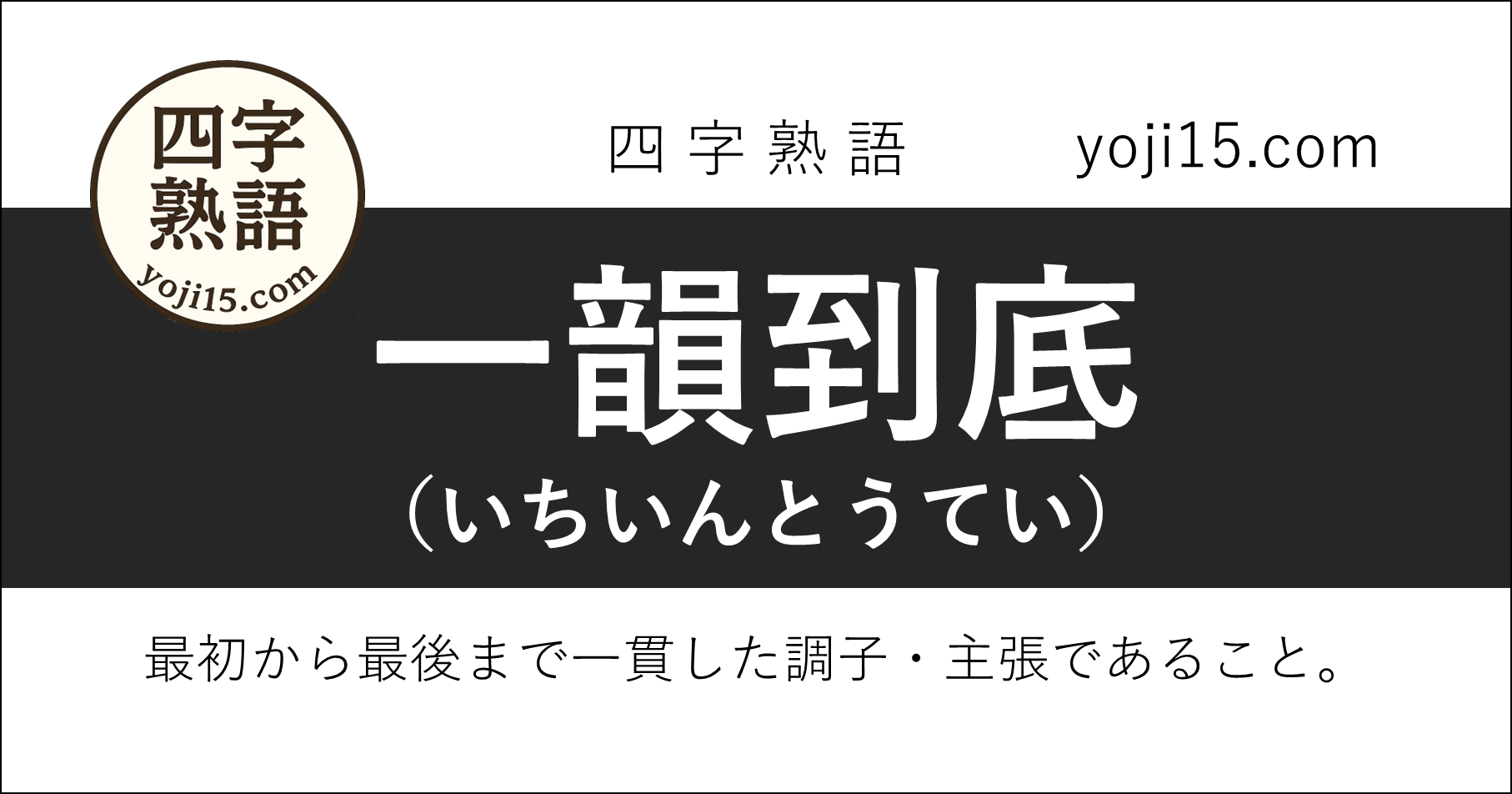
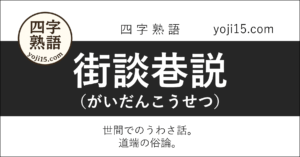
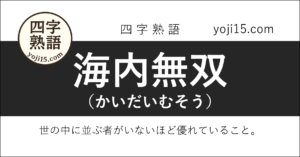
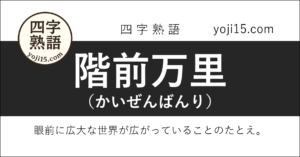
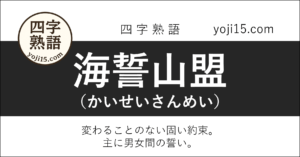
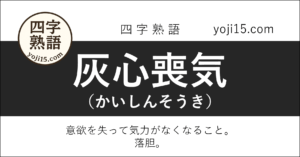
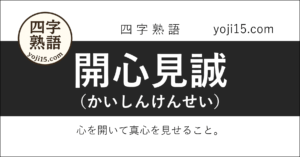
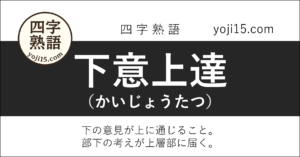
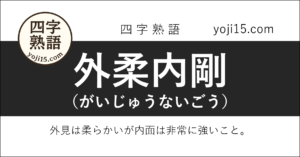
コメント