目次
衣冠束帯の読み方と意味
■ 四字熟語
衣冠束帯(いかんそくたい)
■ 読み方
いかんそくたい
■ 意味
「衣冠束帯」とは、平安時代の公家(くげ)や貴族が公式の場で着用していた正装を指す言葉です。
転じて、「威儀を正した格式ある服装」や「礼儀正しく整った姿」のことも意味します。
- 「衣冠(いかん)」:貴族の衣服と冠(かんむり)
- 「束帯(そくたい)」:貴族の男性が朝廷の儀式などで着用した正式な装束
格式や伝統を重んじた装いを象徴する語句として用いられます。
衣冠束帯の語源と由来
■ 出典・背景
古代から中世の日本(特に平安時代〜鎌倉時代)にかけて、公家や高官が朝廷の儀式などで身につけた服装の様式が「衣冠束帯」です。
「衣冠」も「束帯」もそれぞれが正装を意味する言葉ですが、組み合わせることでより格式の高さが強調されます。
■ 象徴するもの
- 伝統・格式・威厳
- 朝廷文化・古典美
- 礼儀と作法の重視
衣冠束帯の使い方と例文
■ 用例・使い方
- 式典に衣冠束帯の装いで参列した。
- 彼の姿はまるで衣冠束帯の平安貴族のようだった。
- 衣冠束帯の儀式は、日本文化の荘厳さを象徴している。
衣冠束帯と関連する四字熟語
以下は、「衣冠束帯」に関連した意味・イメージを持つ四字熟語です。
| 四字熟語 | 読み方 | 意味 |
|---|---|---|
| 冠婚葬祭 | かんこんそうさい | 伝統的な礼儀・儀式を重視する場面(冠=元服、婚=結婚など) |
| 威風堂堂 | いふうどうどう | 堂々とした威厳のある様子 |
| 正装礼服 | せいそうれいふく | 正式な儀式用の服装 |
| 礼儀作法 | れいぎさほう | 社会における礼儀や作法のこと |
| 典雅荘重 | てんがそうちょう | 上品で厳かな様子 |
衣冠束帯が使われる場面
■ 現代での使われ方
- 伝統行事や再現イベント(例:雅楽の演奏会、時代祭など)
- 歴史小説や時代劇の描写
- 文化論・礼法の文脈で比喩的に使われることも
■ 比喩としての意味
- 「衣冠束帯のごとき振る舞い」=形式ばって堅苦しい態度というネガティブなニュアンスで使われることもあり
まとめ:衣冠束帯は、日本の伝統と格式を映す美しい言葉
「衣冠束帯」は、古代日本の美意識と礼節を象徴する四字熟語です。
本来は具体的な服装を指す語ですが、現代では格式・伝統・儀礼の象徴的な表現としても使われています。
日本文化の深さや礼儀の重要性を伝える、美しい表現の一つといえるでしょう。
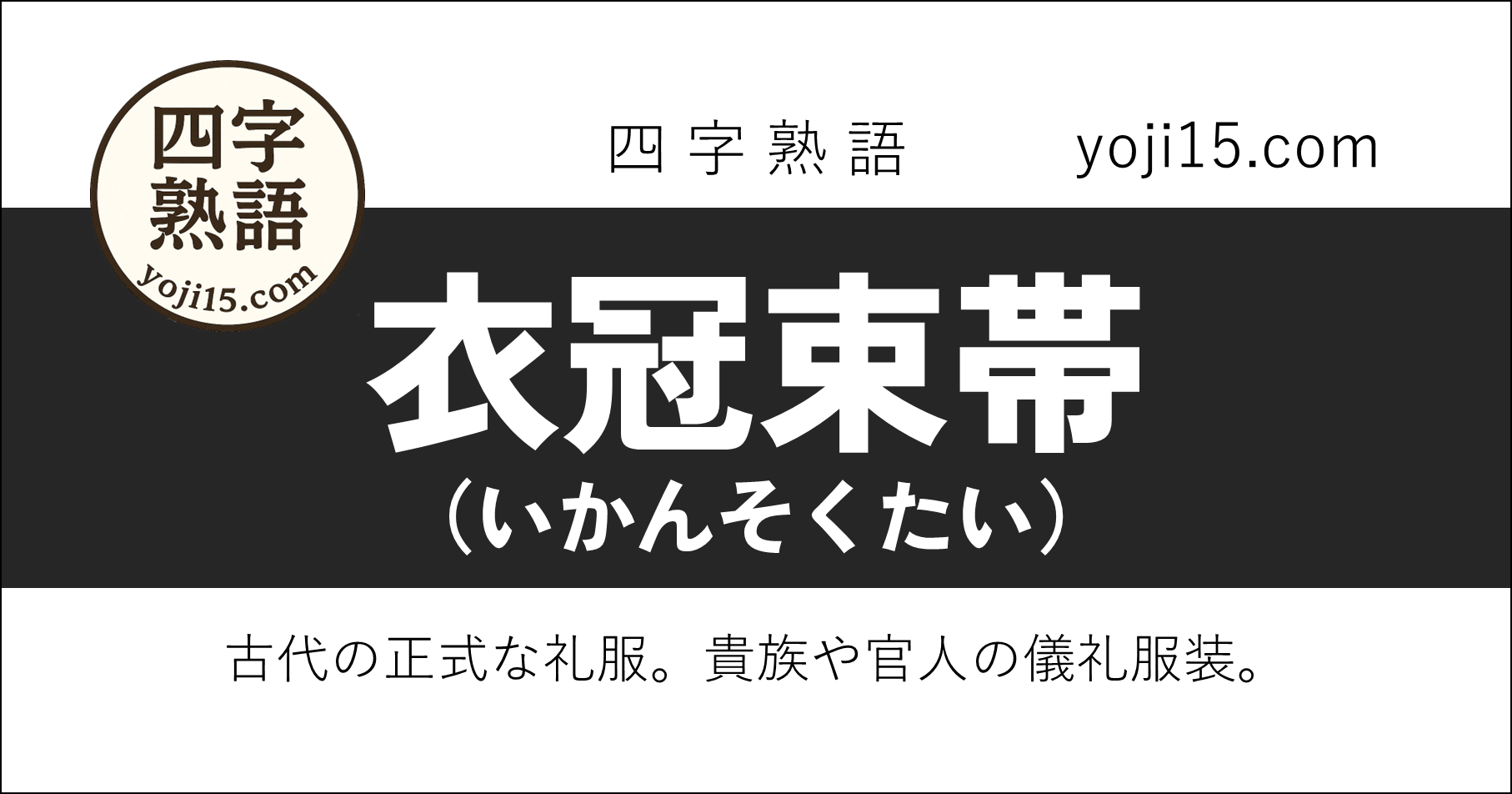
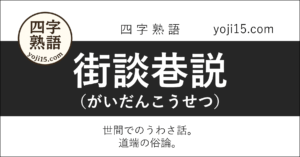
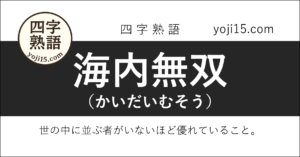
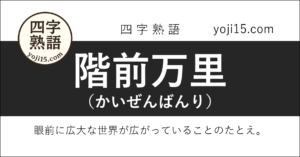
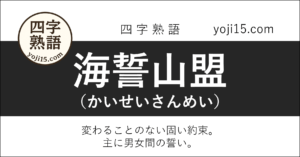
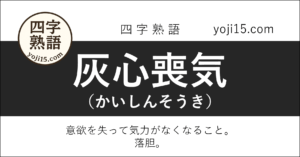
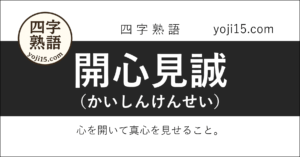
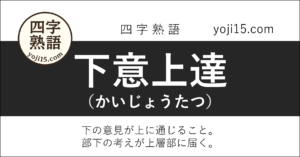
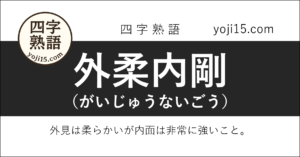
コメント